少しずつ暑さも和らぎ、過ごしやすい時期になり、飼い主さんも秋の訪れを感じているころかと思います。
しかし、秋は過ごしやすい季節の一方で、1日の寒暖差が大きく、愛犬も体調を崩しがちになり、病気を引き起こしやすくなるのです。
そこで、今回は秋に気をつけたい愛犬の体調トラブルとその対策についてご紹介します。

胃腸炎
夏の暑さで胃腸が弱っているところに、昼と夜の寒暖差が大きくなると、体温調節のためにはたらく自律神経が疲弊し、消化器官などの内臓が弱ります。
また、夏の間に落ちていた食欲が急に戻ってくることがあり、暑さで胃腸が弱っているところにいきなり大量に食べることで、消化器トラブルを引き起こすことがあるのです。
症状
胃腸炎になると、食欲不振や嘔吐、下痢などの症状が現れます。
特に、体力のない子犬や老犬には注意が必要です。
対策
食欲にまかせて食事やおやつを与えず、愛犬の様子を見ながら、少しずつ食べる量を増やしましょう。
また、犬は1日の気温差が7℃以上になると、下痢を起こしやすくなると言われているため、室内を犬にとって快適な気温22℃前後、湿度60%前後に保つようにしてください。
それでも、嘔吐や下痢が続く場合には、早目に動物病院を受診することがおすすめです。

関節疾患
夏は暑さを避ける意味でお散歩の時間や回数を減らすなど、運動不足になり筋肉が衰えがちです。
そんな状態で、涼しくなってきたからと急に運動量を増やせば、足腰への負担が大きくなります。
また、寒くなり血行が悪くなることで筋肉がこわばって関節に負担がかかるため、関節トラブルも引き起こしやすくなります。
症状
関節炎を発症すると、関節に痛みや変形、こわばりが生じるため、足を引きずるしぐさを見せるようになります。
対策
上記の症状が見られる場合には、早目に動物病院を受診することがおすすめです。
涼しくなってきたら、急にお散歩の時間や回数を増やすのではなく、足腰への負担を軽減するために、愛犬の様子を見ながら少しずつ運動量を増やすようにしましょう。
特に、朝は散歩の前に軽い運動をし、体を温めてから出かるようにしてください。

泌尿器系疾患
夏場に比べ、涼しくなると水を飲む量が少なくなり、尿の排泄量が減る傾向です。
そのため、膀胱炎や尿路結石などの泌尿器系の病気にかかりやすくなります。
症状
膀胱炎は頻尿や血尿、排尿痛などが特徴的な症状です。
尿路結石はできた場所によって、膀胱結石や尿道結石と呼ばれ、頻尿や血尿、排尿困難などの症状が見られます。
なお、結石が尿道に詰まり排尿ができなくなると、命に関わる場合もあるため注意が必要です。
対策
水を飲む量が減ったなと思ったら、ウェットフードを取り入れるなど水分補給に努めるようにしましょう。
また、犬は寒くなると動くことが億劫になるため、トイレに行くことを我慢し、膀胱炎の発症のリスクが高まることがあるのです。
そのため、カーペットを敷くなど、トイレへの動線を暖かく保ってあげましょう。
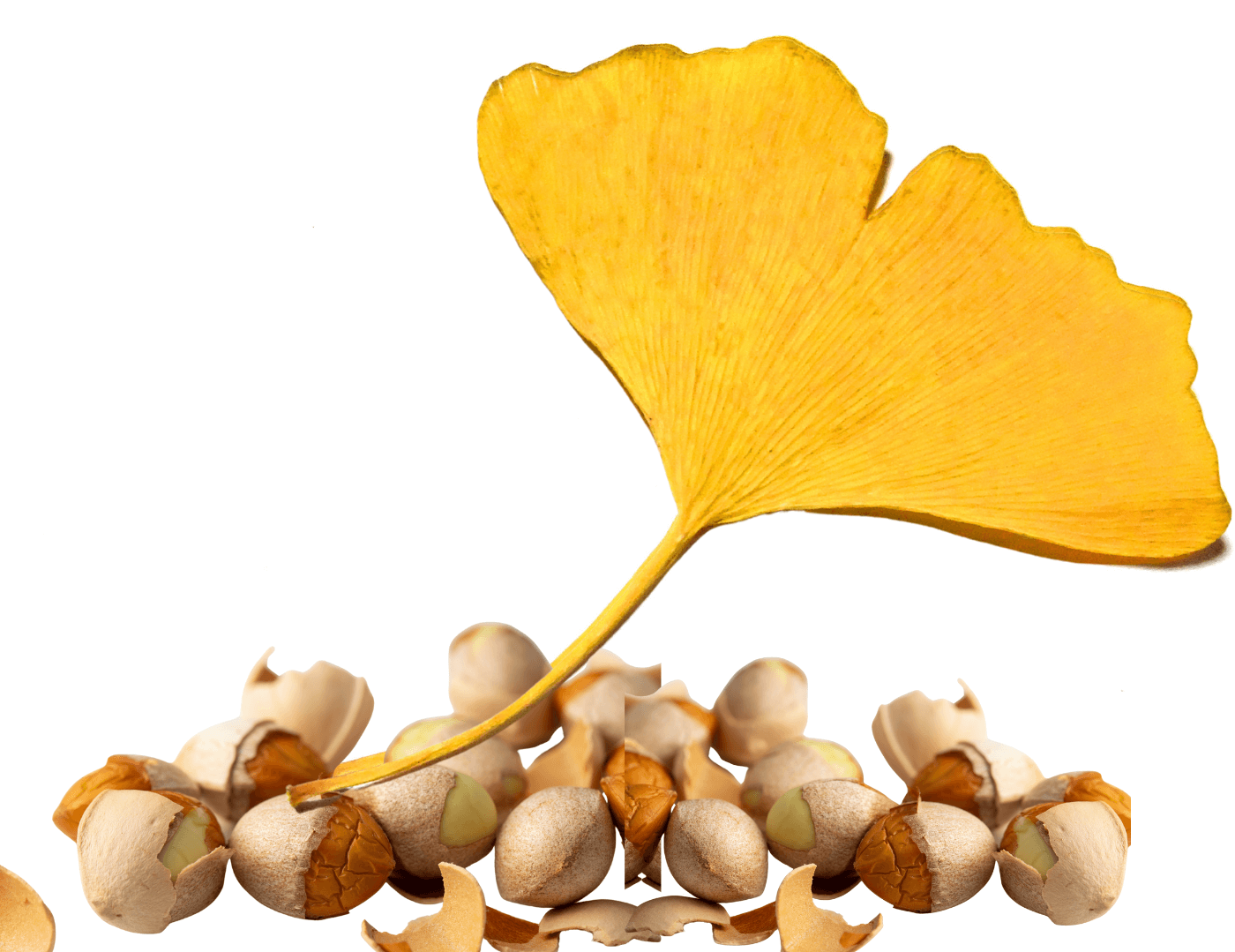
呼吸器疾患
秋は空気が乾燥しているため、のどや鼻の粘膜からウイルスや細菌、真菌(カビ)に感染しやすくなり、肺炎などの呼吸器疾患を引き起こしやすくなります。
さらに、気温の低下と共に体温が下がることで、免疫も低下し、感染症のリスクが高まるのです。
症状
呼吸器疾患になると、激しく咳き込み、気管支や肺に影響を起こします。
犬は人間のような風邪やインフルエンザにはなりませんが、ジステンパーやケンネルコフといった呼吸器症状が現れるウイルスにかかる心配があります。
これらの感染症はワクチン接種で予防できるため、毎年のワクチン接種を欠かさずおこなうようにしましょう。
アレルギー
春だけでなく秋も、ブタクサやヨモギ、カナムグラなどによるアレルギーを起こしやすい季節です。
症状
散歩中や帰宅後に、かゆがる、くしゃみをするなどのアレルギー症状が見られます。
対策
愛犬が花粉にアレルギーがあるとわかった場合は、散歩の際は洋服を着せるなどして、なるべく体に花粉を付着させないようにしましょう。
また、帰宅後にシートなどで体を拭いたりブラッシングをしたりなど、できるだけ体に付着した花粉を落とす工夫をするのもおすすめです。
なお、飼い主さんが衣類に花粉を付けて帰宅する場合もあるため、玄関で上着などの衣類は脱ぐなど、家の中に花粉を持ち込まないように配慮するようにしましょう。
まとめ
秋は過ごしやすい季節でもありますが、1日の気温差が大きく、愛犬が体調を崩しがちになります。
しかし、夏場に落ちていた食欲が戻ったり、散歩の距離や時間を増やしたりと嬉しいことも。
愛犬の様子をしっかり観察しながら、適度な食事や運動、水分補給で季節の変わり目を乗り切りましょう。


